本・新聞−ネパール関連の本(初心者向け)
ネパールをあまりよく知らないという人がネパールを知る上で役に立つかな、と思う本を書きます。これ以外にもそれぞれの専門の本や論文は日本語、英語、一部ネパール語のものがありますが、それはそれぞれに探してもらうことにして、ここでは初心者向けで専門知識がなくても理解できる本だけを書きます。NGOについて知りたい場合は、NGOのwebを見る、あるいは歴史あるNGOであればNGOの方がそれぞれに本を書いていることが多いので、そちらを探してご覧ください。

- 作者: ブラッドリーメイヒュー,ワンダバイブクイン,リンゼイブラウン,Bradley Mayhew,Wanda Vivequin,Lindsay Brown
- 出版社/メーカー: メディアファクトリー
- 発売日: 2004/04
- メディア: 単行本
- クリック: 14回
- この商品を含むブログ (4件) を見る
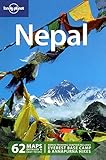
- 作者: Joe Bindloss,Trent Holden,Bradley Mayhew
- 出版社/メーカー: Lonely Planet
- 発売日: 2009/09/01
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 旅行人編集部
- 出版社/メーカー: 旅行人
- 発売日: 2002/08
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 9回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
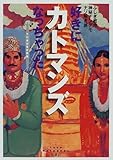
好きになっちゃったカトマンズ―ふしぎ都市 神秘ナンデモナゾ解き旅 (アジア楽園マニュアル)
- 作者: 下川裕治
- 出版社/メーカー: 双葉社
- 発売日: 1998/06
- メディア: 単行本
- クリック: 15回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 日本ネパール協会
- 出版社/メーカー: 明石書店
- 発売日: 2000/09/20
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 29回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 石井溥
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 1997/03
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 9回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 辛島昇,江島恵教,小西正捷,前田専学,応地利明
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2002/04/01
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 辛島昇,応地利明,坂田貞二,前田専学,江島惠教,小西正捷,山崎元一
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2012/05/25
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
World Infopaedia Nepal
Author:C B Upadyay
ISBN:8189645498
ネパールのいろいろなことが調べられる事典。アマゾンでの取り扱いは今のところないらしいが、英語圏の書店で取扱いのあるところがいくつかある。ネパールでも探せば売っていることもある(絶対あるとは限らない)。

- 作者: 田中雅一,田辺明生
- 出版社/メーカー: 世界思想社
- 発売日: 2010/09/29
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 河口慧海
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1978/06/10
- メディア: 文庫
- クリック: 8回
- この商品を含むブログ (18件) を見る

- 作者: トニー・ハーゲン,町田靖治
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 1997/10/01
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
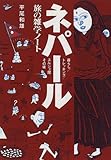
ネパール 旅の雑学ノート―暮らし トレッキング スルジェ館その後
- 作者: 平尾和雄
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 1996/09
- メディア: 単行本
- クリック: 6回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

ヒマラヤの村―シェルパ族とくらす (1976年) (現代教養文庫)
- 作者: 柳本杳美
- 出版社/メーカー: 社会思想社
- 発売日: 1976
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 田村善次郎
- 出版社/メーカー: 武蔵野美術大学出版局
- 発売日: 2004/04
- メディア: 単行本
- クリック: 12回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 石井溥,山本真弓,橘健一,ケシャブ・L.マハラジャン,伊藤ゆき,K.L. Maharjan
- 出版社/メーカー: 東京大学出版会
- 発売日: 2005/07
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
論文なのでとっつきにくく感じる人もいるかもしれないが、専門知識がない人が全く理解できない内容、というわけでもない(と思う)。
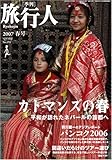
旅行人 2007年春号カトマンズの春〜平和が訪れたネパールの首都へ
- 作者: 田中雅子/平尾和雄/蔵前仁一,旅行人編集部
- 出版社/メーカー: 旅行人
- 発売日: 2007/04/25
- メディア: 雑誌
- クリック: 14回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

ネパールのビール―ベスト・エッセイ集〈’91年版〉 (文春文庫)
- 作者: 日本エッセイストクラブ
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 1994/07
- メディア: 文庫
- クリック: 5回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 瀬尾里枝
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2000/07
- メディア: 文庫
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
ネパールが素朴で好きだとか素晴らしいとか、逆に貧しいとか問題だらけだとかかわいそうだとかそういう感情を書く人は多いけど、それらとは違い、わりとと冷静な視点でいいところも悪いところも淡々と描いている。カトマンズの庶民の生活が垣間見れる。
hontoからもダウンロード可
https://hon-to.jp/asp/ShowSeriesDetail.do?seriesId=B-MBJ-20003-100001291-001-001

- 作者: 中山茂大,阪口克
- 出版社/メーカー: リトル・モア
- 発売日: 2010/02/06
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 8回
- この商品を含むブログ (8件) を見る

ネパールにおけるツーリズム空間の創出―カトマンドゥから描く地域像
- 作者: 森本泉
- 出版社/メーカー: 古今書院
- 発売日: 2012/03/01
- メディア: 単行本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

ネパール王制解体―国王と民衆の確執が生んだマオイスト (NHKブックス)
- 作者: 小倉清子
- 出版社/メーカー: 日本放送出版協会
- 発売日: 2007/01
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 28回
- この商品を含むブログ (12件) を見る

王国を揺るがした60日―1050人の証言・ネパール民主化闘争
- 作者: 小倉清子
- 出版社/メーカー: 亜紀書房
- 発売日: 1999/10/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る

現代ネパールの政治と社会――民主化とマオイストの影響の拡大 (世界人権問題叢書92)
- 作者: 南真木人,石井溥
- 出版社/メーカー: 明石書店
- 発売日: 2015/04/03
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 田中公明,吉崎一美
- 出版社/メーカー: 春秋社
- 発売日: 1998/10
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 5回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 立川武蔵
- 出版社/メーカー: 佼成出版社
- 発売日: 1991/12
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 山口しのぶ
- 出版社/メーカー: 山喜房仏書林
- 発売日: 2005/06
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 立川武蔵
- 出版社/メーカー: せりか書房
- 発売日: 1980/01
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 山下博司
- 出版社/メーカー: 山川出版社
- 発売日: 1997/05/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
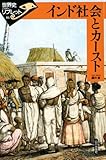
- 作者: 藤井毅
- 出版社/メーカー: 山川出版社
- 発売日: 2007/12/01
- メディア: 単行本
- クリック: 18回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 山本真弓
- 出版社/メーカー: 春風社
- 発売日: 2002/11
- メディア: 単行本
- クリック: 10回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

ネパール人の暮らしと政治―「風刺笑劇」の世界から (中公新書)
- 作者: 山本真弓
- 出版社/メーカー: 中央公論社
- 発売日: 1993/10
- メディア: 新書
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
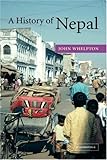
- 作者: John Whelpton
- 出版社/メーカー: Cambridge University Press
- 発売日: 2005/02/17
- メディア: ハードカバー
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: D.B.ビスタ,田村真知子
- 出版社/メーカー: 古今書院
- 発売日: 1982/04
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: ドゥル・バハドゥールビスタ,Dor Bahadur Bista,田村真知子
- 出版社/メーカー: 古今書院
- 発売日: 1993/06
- メディア: 単行本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: Dor Bahadur Bista
- 出版社/メーカー: Ratna Pustak Bhandar,Nepal
- 発売日: 2004/07/31
- メディア: ハードカバー
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: ねこぢる
- 出版社/メーカー: 青林堂
- 発売日: 2001/04
- メディア: コミック
- 購入: 1人 クリック: 47回
- この商品を含むブログ (45件) を見る

- 作者: 西原 理恵子
- 出版社/メーカー: 毎日新聞社
- 発売日: 2011/01/25
- メディア: 単行本
- 購入: 8人 クリック: 165回
- この商品を含むブログ (42件) を見る

- 作者: 池澤夏樹
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2000/09
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (6件) を見る

- 作者: 井上靖
- 出版社/メーカー: KADOKAWA
- 発売日: 1975/03
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (3件) を見る

TRANSIT(トランジット)5号 ~ヒマラヤ特集 美しきヒマラヤが呼んでいる~ (講談社MOOK) (講談社 Mook)
- 作者: 講談社
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2009/06/05
- メディア: ムック
- 購入: 3人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (12件) を見る

coyote(コヨーテ)No.5 特集・チベット、ヒマラヤへと続く道「ダライ・ラマもこの道を旅した」
- 作者: 新井敏記
- 出版社/メーカー: スイッチパブリッシング
- 発売日: 2005/04/10
- メディア: ムック
- 購入: 1人 クリック: 3回
- この商品を含むブログ (10件) を見る
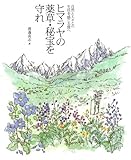
- 作者: 渡邊高志
- 出版社/メーカー: ワニブックス
- 発売日: 2008/05
- メディア: 大型本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 大場秀章
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1999/06/25
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る

エベレスト花の道―ヒマラヤ・フラワートレッキング (コロナ・ブックス)
- 作者: 藤田弘基
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2003/03/01
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る

エベレスト花街道を行く―ヒマラヤに咲く花の競演 (講談社カルチャーブックス)
- 作者: 藤田弘基
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1997/07
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
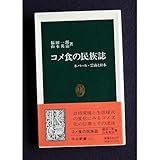
- 作者: 福田一郎,山本英治
- 出版社/メーカー: 中央公論社
- 発売日: 1993/02/01
- メディア: 新書
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
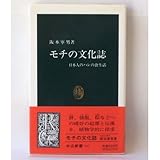
- 作者: 阪本寧男
- 出版社/メーカー: 中央公論社
- 発売日: 1989/11
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 小野一男,湯舟貞子
- 出版社/メーカー: ふくろう出版
- 発売日: 2009/05
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 今野道勝
- 出版社/メーカー: 山と渓谷社
- 発売日: 1982/06
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 山内乾史,杉本均,内田康雄,米原あき,樋口とみ子,小原優貴,畠博之,宮本万里,日下部達哉,小川啓一
- 出版社/メーカー: 学文社
- 発売日: 2006/09/30
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログを見る

ネパールの被抑圧者集団の教育問題―タライ地方のダリットとエスニック・マイノリティ集団の学習阻害/促進要因をめぐって
- 作者: 畠博之
- 出版社/メーカー: 学文社
- 発売日: 2008/01/01
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 川床靖子
- 出版社/メーカー: 春風社
- 発売日: 2007/05/01
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 15回
- この商品を含むブログ (4件) を見る

- 作者: 吉永マサユキ
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2010/08/05
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 大野哲也
- 出版社/メーカー: 世界思想社
- 発売日: 2012/06/28
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 1人 クリック: 114回
- この商品を含むブログ (7件) を見る