サービス−ネパールの衛星放送のチャンネル Satellite Channels
■ネパールでみられる衛星放送
衛星放送の契約をすれば、ネパール国外のチャンネルも見られる。ここには見たものほぼすべてを書いているが、数種類契約法があるらしく、たとえばNHK worldが見られる契約とみられない契約があるように、すべてのチャンネルがすべてのテレビで見られるわけではない。
衛星放送の会社のサイト
http://www.dishhome.com.np/
http://www.dthnepal.com/index.html
全体の傾向としてはインド関連(音楽、ドラマ、映画、スポーツ、宗教)が多い。それ以外はNHKworldやアリランのような各国のPRのチャンネルなど。MTVやstarなどはグローバルなチャンネルだがインドの地域色の出ている放送内容。ディスカバリーチャンネル、FOX、BBCなどの英語圏のチャンネルは日本のケーブルテレビのものとあまり変わらない内容。
大体の番組は英語かヒンディー語なので、それらがわかれば楽しめる。NHKworldやアリランなどの非英語圏の番組も基本的に英語吹き替えか字幕がでる。
【衛星放送で見られるテレビ局一覧】
- HBO(アメリカ、ドキュメンタリーその他)http://www.hbo.com/
- National Geographic (自然)http://www.nationalgeographic.com/
- MTV India 音楽(インドの音楽、洋楽)http://mtv.in.com/
- zoom tv(インドの音楽、芸能)http://www.zoomtv.in/
- etc(インドの音楽、芸能)http://www.etc.in/
- Z Cinema (インドの映画)
- Z Smile (インドのドラマ)
- AXN (洋画) http://www.entertainmentasiatv.com/?redirect=axn-asia
- INDIA TV (インドのニュース)
- Animal Planet (動物)http://animal.discovery.com/
- Filmax (洋画)
- Nick (日本、イギリスその他のアニメ。パーマンのヒンディー語吹き替えなども。)http://www.nickindia.com/
- Neo Cricket (クリケット)
- Neo Sports (スポーツ)
- Zee TV (インドのドラマ)
- Filmy (インドの映画)
- Ten Sports (サッカーなどスポーツ)
- MD?TV imagine (インドのドラマ)
- S Max (インドの映画)
- Discoverty Channel (冒険)http://dsc.discovery.com/
- Star न्यूज (インドのニュース)
- Disney Channel (アメリカのアニメやドラマ、インドのアニメやドラマ半々くらい)http://www.disney.in/DisneyChannel/
- Samara One (インドのドラマ)
- Star Cricket (クリケット)
- संस्कार (ヒンドゥー教のグルが歌ってる)
- Fashion TV (いろいろな国のコレクションなどファッション) http://www.ftv.com
- Star Gold (インドの映画)
- Colors (インドのドラマ)
- Star one (インドのドラマ)
- Fox History (歴史)http://www.foxhistory.com/MainPage.aspx
- BBC (イギリスのニュース)http://www.bbc.co.uk/
- आस्था (ヒンドゥー教のグルが歌う)
- Star movies (イギリスの?映画)
- ARY Qtv (アラビア語?イスラム教関係?)
- Sony (インドのドラマほか)
- Star Plus (インドのドラマほか)
- JETIX (アニメ、戦隊もののようなドラマなど)
- NHK World(日本関連の英語と日本語のニュース、そのほかNHKの番組、ニュース率高い)http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/japanese/top/index.html
- arirang TV(韓国。ニュースが多いが音楽番組なども)http://www.arirang.co.kr/index.asp
- CCTV(中国)http://english.cntv.cn/01/index.shtml
- CNN(アメリカのニュース)http://edition.cnn.com/
- Aljazeera(中東、アフリカのニュース)http://english.aljazeera.net/
■ネパールで日本のテレビを見る
NHKWorldはUstreamでも配信を始めたので、テレビがなくてもネット環境が良ければ見ることができます。ネパールだと回線速度が遅いところも結構あるから微妙だと思うが。
http://www.ustream.tv/nhkworld
KeyHoleTVをダウンロードしてインストールするとどこでも(インターネットの環境にさえあれば)日本のテレビやラジオが聴けますので、この方法で日本のテレビやラジオをネパールで視る・聞くという手もあります。ただ、画像が荒い、ラジオは時々途切れるのと、いつまでこのサービスが利用できるか、は不明です。
http://www.v2p.jp/video/
日本のテレビをインターネット経由で海外でも見られるようにするslingboxというももあります(未だ試していないのでネパールでどれだけ使えるかわかりませんが)。
http://www.slingbox.jp/
TV-recでも見れるとありますが(未だ試していないのでネパールでどれだけ使えるかはわかりませんが)
http://www.tv-rec.com/index.html
海外で日本のテレビを見る方法 http://matome.naver.jp/odai/2132780018749461701
本・新聞−新聞・雑誌
- Kantipur http://www.ekantipur.com/en/
- Naya Patrika http://nayapatrika.com/
- Annapurna Post http://www.annapurnapost.com/
- Samachar Patra http://www.newsofnepal.com/non/
- Gorkha Patra(The Rising Nepal) http://www.gorkhapatra.org.np/
- Rajdhani http://www.rajdhani.com.np/
- Nagarik http://www.nagariknews.com/
- The Himalayan Times http://www.thehimalayantimes.com/
- Saptahik http://www.ekantipur.com/saptahik/
- Republica http://www.myrepublica.com/portal/
- The Kathmandu Post http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/
- Nari http://www.ekantipur.com/nari/
- Nepali times http://www.nepalitimes.com/
- Himal http://www.himalmag.com/
- vow http://www.vownepal.com/portal/
- The boss http://www.readtheboss.com/portal/index.php
- New Spotlight http://www.spotlightnepal.com/
- New Business Age http://newbusinessage.com/
- Wave http://www.wavemag.com.np/
- y! http://www.yzine.com.np/#/home
- The organisation http://www.odcincorp.com/theorganisation.php
- Today's Youth Asia http://www.facebook.com/todaysyouthasia
- Global Nepali http://globalnepalimag.wordpress.com/
- Nepalese Economic Review http://www.ner.com.np/
- ECC Nepal http://www.ecs.com.np/index.php
- Sujeevshakya http://www.sujeevshakya.com/index.php
※アプリでネパールのニュースが読めるものもいくつかあるので、アンドロイドマーケットなどでnepalで検索してみてください。(日本語で書かれたものはなくても英語で書かれたものはあります。)
サービス−ラジオ Radio Stations
- 都市ではたくさんのラジオ局がある。地方や僻地は聞けるラジオ局が少ない。
- 全部の局を聴いたわけではないが、全体としてはニュース、ネパールの音楽か洋楽(80年代のものが多い?)が流れて、視聴者からリクエストをもらい、少し会話をして音楽を流す、みたいなのが多い(テレビと同様)。あとラジオドラマみたいなのも時々ある。
- 代表的なものはRadio Nepalで、これはネパール全土で(へき地も含み)聴けるようになっている。一日中放送しているわけではなく、一日三回の放送で、おもに国内ニュースがネパール語、英語、ヒンディー語などそのほかの言語で聞ける。新聞もないようなへき地にしばらく住むことになっても、最低限これだけは聴ける(ただ、国外ニュースの割合が少ないので、ネパール以外の日本やそれ以外の国で何が起こっているのかを知ることは難しい。日本の首相が変わったことさえわからなかったりする。)
- カトマンズなどの都市ではたくさんの局があり、BBCも聴けるので、ネパール国外のニュースはこれで間に合う。ただ、日本関連のラジオはNHKのラジオ日本(短波)があるが、実質ラジオを通して聴くのは難しく、ネットを通して視聴となる。UstreamでNHK Worldも聞けるのでネットで聞くならそちらを聞いてもいいかもしれない。(別エントリー参照)
- ラジオ本体はネパールの電化製品の取り扱いのある店で売っている。1000ルピーもあれば買える。
- 最近はネパール国外でもustreamやmediaplayerなどでネパールのラジオが聴けるようになってきているのでそれぞれのサイトでnepalで検索してみると見つかる。ネパールのラジオなどが聴けるアプリも増えているのでアンドロイドマーケットでnepalなど検索してみるとみつかる。
ラジオ局一覧
http://radiostationworld.com/locations/nepal/radio_websites.asp
http://www.dthnepal.com/fmradio.htm
Nepal International Television Network
http://www.nepalchannels.com/index.jsp
ネパールのラジオをインターネット経由で聞けるサイト(ネパール国外でも聞ける)
Entertainmentnepal
http://www.entertainmentnepal.net/
mediaplayerなどで一部のラジオ局の番組が聴ける。
Nepali FM(itunesのアプリ)
http://itunes.apple.com/jp/app/nepali-fm/id323648903?mt=8
ネパールのラジオが聴けるアプリ。
Radio Nepal
http://www.radionepal.org/
アンドロイドのアプリもあり。
BBC south asia
http://www.bbc.co.uk/news/world/south_asia/
本・新聞−ネパール関連の本(初心者向け)
ネパールをあまりよく知らないという人がネパールを知る上で役に立つかな、と思う本を書きます。これ以外にもそれぞれの専門の本や論文は日本語、英語、一部ネパール語のものがありますが、それはそれぞれに探してもらうことにして、ここでは初心者向けで専門知識がなくても理解できる本だけを書きます。NGOについて知りたい場合は、NGOのwebを見る、あるいは歴史あるNGOであればNGOの方がそれぞれに本を書いていることが多いので、そちらを探してご覧ください。

- 作者: ブラッドリーメイヒュー,ワンダバイブクイン,リンゼイブラウン,Bradley Mayhew,Wanda Vivequin,Lindsay Brown
- 出版社/メーカー: メディアファクトリー
- 発売日: 2004/04
- メディア: 単行本
- クリック: 14回
- この商品を含むブログ (4件) を見る
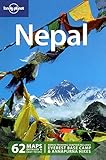
- 作者: Joe Bindloss,Trent Holden,Bradley Mayhew
- 出版社/メーカー: Lonely Planet
- 発売日: 2009/09/01
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 旅行人編集部
- 出版社/メーカー: 旅行人
- 発売日: 2002/08
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 9回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
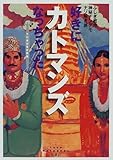
好きになっちゃったカトマンズ―ふしぎ都市 神秘ナンデモナゾ解き旅 (アジア楽園マニュアル)
- 作者: 下川裕治
- 出版社/メーカー: 双葉社
- 発売日: 1998/06
- メディア: 単行本
- クリック: 15回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 日本ネパール協会
- 出版社/メーカー: 明石書店
- 発売日: 2000/09/20
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 29回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 石井溥
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 1997/03
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 9回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 辛島昇,江島恵教,小西正捷,前田専学,応地利明
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2002/04/01
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 辛島昇,応地利明,坂田貞二,前田専学,江島惠教,小西正捷,山崎元一
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2012/05/25
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
World Infopaedia Nepal
Author:C B Upadyay
ISBN:8189645498
ネパールのいろいろなことが調べられる事典。アマゾンでの取り扱いは今のところないらしいが、英語圏の書店で取扱いのあるところがいくつかある。ネパールでも探せば売っていることもある(絶対あるとは限らない)。

- 作者: 田中雅一,田辺明生
- 出版社/メーカー: 世界思想社
- 発売日: 2010/09/29
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 河口慧海
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1978/06/10
- メディア: 文庫
- クリック: 8回
- この商品を含むブログ (18件) を見る

- 作者: トニー・ハーゲン,町田靖治
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 1997/10/01
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
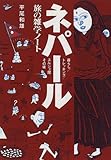
ネパール 旅の雑学ノート―暮らし トレッキング スルジェ館その後
- 作者: 平尾和雄
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 1996/09
- メディア: 単行本
- クリック: 6回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

ヒマラヤの村―シェルパ族とくらす (1976年) (現代教養文庫)
- 作者: 柳本杳美
- 出版社/メーカー: 社会思想社
- 発売日: 1976
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 田村善次郎
- 出版社/メーカー: 武蔵野美術大学出版局
- 発売日: 2004/04
- メディア: 単行本
- クリック: 12回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 石井溥,山本真弓,橘健一,ケシャブ・L.マハラジャン,伊藤ゆき,K.L. Maharjan
- 出版社/メーカー: 東京大学出版会
- 発売日: 2005/07
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
論文なのでとっつきにくく感じる人もいるかもしれないが、専門知識がない人が全く理解できない内容、というわけでもない(と思う)。
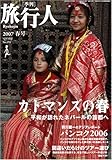
旅行人 2007年春号カトマンズの春〜平和が訪れたネパールの首都へ
- 作者: 田中雅子/平尾和雄/蔵前仁一,旅行人編集部
- 出版社/メーカー: 旅行人
- 発売日: 2007/04/25
- メディア: 雑誌
- クリック: 14回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

ネパールのビール―ベスト・エッセイ集〈’91年版〉 (文春文庫)
- 作者: 日本エッセイストクラブ
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 1994/07
- メディア: 文庫
- クリック: 5回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 瀬尾里枝
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2000/07
- メディア: 文庫
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
ネパールが素朴で好きだとか素晴らしいとか、逆に貧しいとか問題だらけだとかかわいそうだとかそういう感情を書く人は多いけど、それらとは違い、わりとと冷静な視点でいいところも悪いところも淡々と描いている。カトマンズの庶民の生活が垣間見れる。
hontoからもダウンロード可
https://hon-to.jp/asp/ShowSeriesDetail.do?seriesId=B-MBJ-20003-100001291-001-001

- 作者: 中山茂大,阪口克
- 出版社/メーカー: リトル・モア
- 発売日: 2010/02/06
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 8回
- この商品を含むブログ (8件) を見る

ネパールにおけるツーリズム空間の創出―カトマンドゥから描く地域像
- 作者: 森本泉
- 出版社/メーカー: 古今書院
- 発売日: 2012/03/01
- メディア: 単行本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

ネパール王制解体―国王と民衆の確執が生んだマオイスト (NHKブックス)
- 作者: 小倉清子
- 出版社/メーカー: 日本放送出版協会
- 発売日: 2007/01
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 28回
- この商品を含むブログ (12件) を見る

王国を揺るがした60日―1050人の証言・ネパール民主化闘争
- 作者: 小倉清子
- 出版社/メーカー: 亜紀書房
- 発売日: 1999/10/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る

現代ネパールの政治と社会――民主化とマオイストの影響の拡大 (世界人権問題叢書92)
- 作者: 南真木人,石井溥
- 出版社/メーカー: 明石書店
- 発売日: 2015/04/03
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 田中公明,吉崎一美
- 出版社/メーカー: 春秋社
- 発売日: 1998/10
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 5回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 立川武蔵
- 出版社/メーカー: 佼成出版社
- 発売日: 1991/12
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 山口しのぶ
- 出版社/メーカー: 山喜房仏書林
- 発売日: 2005/06
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 立川武蔵
- 出版社/メーカー: せりか書房
- 発売日: 1980/01
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 山下博司
- 出版社/メーカー: 山川出版社
- 発売日: 1997/05/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
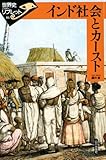
- 作者: 藤井毅
- 出版社/メーカー: 山川出版社
- 発売日: 2007/12/01
- メディア: 単行本
- クリック: 18回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 山本真弓
- 出版社/メーカー: 春風社
- 発売日: 2002/11
- メディア: 単行本
- クリック: 10回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

ネパール人の暮らしと政治―「風刺笑劇」の世界から (中公新書)
- 作者: 山本真弓
- 出版社/メーカー: 中央公論社
- 発売日: 1993/10
- メディア: 新書
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
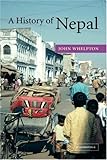
- 作者: John Whelpton
- 出版社/メーカー: Cambridge University Press
- 発売日: 2005/02/17
- メディア: ハードカバー
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: D.B.ビスタ,田村真知子
- 出版社/メーカー: 古今書院
- 発売日: 1982/04
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: ドゥル・バハドゥールビスタ,Dor Bahadur Bista,田村真知子
- 出版社/メーカー: 古今書院
- 発売日: 1993/06
- メディア: 単行本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: Dor Bahadur Bista
- 出版社/メーカー: Ratna Pustak Bhandar,Nepal
- 発売日: 2004/07/31
- メディア: ハードカバー
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: ねこぢる
- 出版社/メーカー: 青林堂
- 発売日: 2001/04
- メディア: コミック
- 購入: 1人 クリック: 47回
- この商品を含むブログ (45件) を見る

- 作者: 西原 理恵子
- 出版社/メーカー: 毎日新聞社
- 発売日: 2011/01/25
- メディア: 単行本
- 購入: 8人 クリック: 165回
- この商品を含むブログ (42件) を見る

- 作者: 池澤夏樹
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2000/09
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (6件) を見る

- 作者: 井上靖
- 出版社/メーカー: KADOKAWA
- 発売日: 1975/03
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (3件) を見る

TRANSIT(トランジット)5号 ~ヒマラヤ特集 美しきヒマラヤが呼んでいる~ (講談社MOOK) (講談社 Mook)
- 作者: 講談社
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2009/06/05
- メディア: ムック
- 購入: 3人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (12件) を見る

coyote(コヨーテ)No.5 特集・チベット、ヒマラヤへと続く道「ダライ・ラマもこの道を旅した」
- 作者: 新井敏記
- 出版社/メーカー: スイッチパブリッシング
- 発売日: 2005/04/10
- メディア: ムック
- 購入: 1人 クリック: 3回
- この商品を含むブログ (10件) を見る
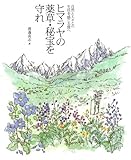
- 作者: 渡邊高志
- 出版社/メーカー: ワニブックス
- 発売日: 2008/05
- メディア: 大型本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 大場秀章
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1999/06/25
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る

エベレスト花の道―ヒマラヤ・フラワートレッキング (コロナ・ブックス)
- 作者: 藤田弘基
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2003/03/01
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る

エベレスト花街道を行く―ヒマラヤに咲く花の競演 (講談社カルチャーブックス)
- 作者: 藤田弘基
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1997/07
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
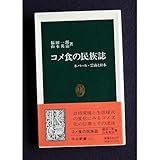
- 作者: 福田一郎,山本英治
- 出版社/メーカー: 中央公論社
- 発売日: 1993/02/01
- メディア: 新書
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
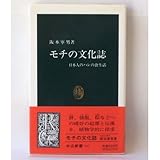
- 作者: 阪本寧男
- 出版社/メーカー: 中央公論社
- 発売日: 1989/11
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 小野一男,湯舟貞子
- 出版社/メーカー: ふくろう出版
- 発売日: 2009/05
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 今野道勝
- 出版社/メーカー: 山と渓谷社
- 発売日: 1982/06
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 山内乾史,杉本均,内田康雄,米原あき,樋口とみ子,小原優貴,畠博之,宮本万里,日下部達哉,小川啓一
- 出版社/メーカー: 学文社
- 発売日: 2006/09/30
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログを見る

ネパールの被抑圧者集団の教育問題―タライ地方のダリットとエスニック・マイノリティ集団の学習阻害/促進要因をめぐって
- 作者: 畠博之
- 出版社/メーカー: 学文社
- 発売日: 2008/01/01
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 川床靖子
- 出版社/メーカー: 春風社
- 発売日: 2007/05/01
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 15回
- この商品を含むブログ (4件) を見る

- 作者: 吉永マサユキ
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2010/08/05
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 大野哲也
- 出版社/メーカー: 世界思想社
- 発売日: 2012/06/28
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 1人 クリック: 114回
- この商品を含むブログ (7件) を見る
本・新聞−ネパール基本情報
- CIA The World Factbook Nepal https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html
- The State Department Nepal http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/bgnotes/sa/nepal9501.html
- U.S. Department of State Nepal http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5283.htm

- 作者: アジア経済研究所
- 出版社/メーカー: アジア経済研究所
- 発売日: 2011/06/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
本・新聞−ネパール関係の本(子供向け)
そんなに多くないですが子供向けの本で、ネパール関連のものもあります。アマゾンでも売っているし、市立図書館などで所蔵しているものも多く、入手はそれほど困難ではありません。

- 作者: エルジェ,川口恵子
- 出版社/メーカー: 福音館書店
- 発売日: 1983/11/25
- メディア: 大型本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

あくまのおよめさん―ネパールの民話 (こどものとも世界昔ばなしの旅)
- 作者: 稲村哲也,結城史隆,イシュワリカルマチャリャ,Ishwari Karmacharya
- 出版社/メーカー: 福音館書店
- 発売日: 1997/11/15
- メディア: 大型本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (8件) を見る

- 作者: 大塚勇三,秋野亥左牟
- 出版社/メーカー: 福音館書店
- 発売日: 1992/02/10
- メディア: ハードカバー
- クリック: 7回
- この商品を含むブログ (7件) を見る

- 作者: 森下裕美
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1989/08/25
- メディア: コミック
- 購入: 1人 クリック: 2回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 松岡享子
- 出版社/メーカー: こぐま社
- 発売日: 1997/02/01
- メディア: 単行本
- クリック: 16回
- この商品を含むブログ (20件) を見る
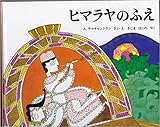
- 作者: A.ラマチャンドラン,A・ラマチャンドラン,きじまはじめ
- 出版社/メーカー: 木城えほんの郷
- 発売日: 2013/01/01
- メディア: 大型本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

絵本メクラとビッコとセムシのはなし―ネパール民話 (1973年)
- 作者: 伊藤昭,熊谷佳也子
- 出版社/メーカー: 下総書房
- 発売日: 1973
- メディア: ?
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
ネパールガエルの冒険
http://www6.ocn.ne.jp/~aiueo/f-frog.html
ネパールの子供向けのお話(絵本)を日本語や英語などに訳したもの。ネパールの書店でも売られています。
サービス−図書館、図書室 Libraries
ネパールには大学やその他の図書館、図書室がある。
全体として管理がずさんで、欠本が多かったり、番号に関係なくばらばらに置いてあったり、本の保存状態が悪かったり、OPACがサーバーダウンが多くまともに使えなかったり、停電でコピーができなかったりと日本と比べるといろいろ問題を抱えているように見えるところが少なくない(管理しているネパール人はそう感じていないのかもしれないが。)借りるときもカードが未だ使われており、バーコードでの管理がなされているところはほとんどない。
個人的には大学や国の図書館よりも民間の図書館、図書室のほうが管理がちゃんとなされていて使いやすい傾向があるように思う。特に大手のINGOの図書室はそれぞれの分野の本のネパールに関するものであれば比較的充実していると言える。ただ、INGOの図書室は基本そこで働く人のためのものなので、好意で使わせてもらう、という形になる。閲覧のみで貸出できない場合が多い。入口で身分証明書の提示を求められることが多い。
digital himalayaのようなデジタルライブラリもあるので、そちらにある資料はそちらで探したほうが確実でかつどこでも見れる。
国際機関のレポートは世銀、ADBはほぼ全て(過去の古いものも全て)それぞれのサイトの中を探せばpdfファイルがダウンロードできる。ユニセフ、UNDP、ILO、UNESCOはそれぞれのサイトからダウンロードできるものとできないものがあり、古いものはダウンロードできないことが多い。直接ヘッドオフィスなどに行けば報告書を分けてくれることもあるが、機関によって対応が異なる。
各国の援助機関も同様で、新しいものはダウンロードできることもあるが、古いものはできないことが多い。JICAは新しいレポートはJICAのサイトからダウンロードできるものもあるし http://www.jica.go.jp/jica-ri/archives/index.html 、JICA図書館(東京)に古いものも保管してあり、一部pdfがダウンロードできるようになっている。https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/Index.html
ネパール政府関係機関もここ数年は国家計画や一部の報告書やサーベイをpdfでダウンロードできるようにしている。ただ、ネパール政府関係機関はupされているファイルの一部が欠けていたりサーバーダウンなど色々トラブルがあるのでそれほどあてにならない。
全体として言えるのは、ネパールに関するものは(日本の図書館よりも)多いが、それ以外の国に関するものや、それぞれの専門の基本的な文献などは少ないということ。また、古い資料は日本やアメリカ、イギリスなどの図書館のほうが多く、きちんと保管している傾向にあるため、そちらをあたったほうが早くスムーズであることが多い。データベースなどで日本の図書館にある資料を検索し、それでも見つからないものをネパールで探す(OPACがあればそれで探す、あるいは本棚を見ていて偶然見つかるかも)という姿勢で使う方が無駄な労力がなくてすむ。WBやADBなど古い報告書も全てダウンロードできるようにしている一部機関を除き、古い報告書を保管している機関は少ないため、10年以上前にものを入手すべく探してもみつからない(司書が参考調査してもみつからない)ことも少なくない。各機関がきちんとデジタルデータ(pdf)で保管し、webで公開するべきなのではと思うが。。。
日本にも国連大学や国際機関の日本事務所がいくつかあり、そこに図書室や資料室がある。ただ、ネパール関連の資料は日本の事務所にはないことが多く、職員も海外の事業について詳しく知っているわけではない。ネパールのことはネパールの事務所で聞いて(あるいはネパール事務所のwebで検索して)探した方が見つかることが多い。日本にある事務所で見れるとしたら一部の統計や報告書だが、それらについてもwebcatに登録しているような大学や研究機関の方が多く所蔵していることが多い(特に古いものは)。なので、大学や研究機関に所属していないから使えないなどの理由がない限りあえて行くメリットはないと思う。
■カトマンズ周辺にある図書館、図書室 (Libraries in Kathmandu)
・National Archives of Nepal
http://nationalarchives.gov.np/
・Tribhuvan University Central Library
http://www.tucl.org.np/
OPACがサーバーダウンのため?使えないことが多いような。
・KATHMANDU UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
http://kucl.ku.edu.np/opac/books.asp
・Martin Chautari
http://www.martinchautari.org.np/
管理がしっかりしている。
・SOCIAL SCIENCE BAHA
http://www.soscbaha.org/
有料会員制。
・South Asia Institute, University of Heidelberg, Kathmandu Branch Office
http://www.sai.uni-heidelberg.de/kathmandu/
図書室あり。
・Nepal National Library
http://www.nnl.gov.np/
OPAC http://library.nnl.gov.np/
・Kaiser Library
http://www.klib.gov.np/
・Nepal Development Research Institute (NDRI)
http://www.ndri.org.np/
※研究所がメイン、図書館というよりレポートのダウンロード可。
・Institute for Integrated Development Studies (IIDS)
http://www.iids.org.np/
図書室あり。
・Institute for foreign affairs
http://www.ifa.org.np/
図書室あり。
・Public Information Center
http://www.bishwabank.org.np/
http://go.worldbank.org/UCTWYM3ZF0
世銀の資料など。貸し出しもコピーも原則不可。
・UNESCO Office in Kathmandu
http://www.unesco.org/new/en/kathmandu/
図書室あり。
・UNHouseの図書室
http://unic.un.org/imucms/kathmandu/35/98/home.aspx
http://unic.un.org/imucms/kathmandu/35/926/reference-library.aspx
比較的新しい国連関連の資料がある(古いものは少ない)。会議で使えないことが多いような。。。
・CBSの図書室(CBSの建物の中)
http://www.cbs.gov.np/
統計は豊富
・Action Aidの図書室
http://www.actionaid.org/nepal
援助関連の資料が充実。
・Forest actionの図書室
http://www.forestaction.org/
森林関連の資料が充実。雑誌も発行している。
・IUCN Nepalの図書室
http://www.iucnnepal.org/
IUCNの活動している分野の資料は比較的あるほう。
■デジタルライブラリ
・digital himalaya
http://www.digitalhimalaya.com/
・Nepal Journals Online
http://www.nepjol.info/
・UN Nepal Information Platform
http://www.un.org.np/
・ICIMOD Himalayan Document Centre
http://www.icimod.org/himaldoc
過去の報告書は一部書店で売っているようなものを除きほぼ全てダウンロード可。クマルタールのオフィスにある図書室も充実。
・forestrynepal
http://www.forestrynepal.org/
森林関連の文献が豊富。ダウンロードできるものも多い。
・Himalayan Research Bulletin
http://digitalcommons.macalester.edu/himalaya/all_issues.html
ほとんど全ての号がダウンロード可
・Indiana University Digital Library of the Commons
http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc
ネパールの森林やコモンズ関連の論文が多い。
・The Tibetan and Himalayan Library (THL)
http://www.thlib.org/index.php
チベット、ヒマラヤ関連のデジタルライブラリ。
・ヒマラヤ学誌
http://www.yunnan-k.jp/yunnan-k/hsm.html
ネパール、ブータンなどヒマラヤ関連の論文が載っている。一部webから見れる論文もあり。(バックナンバーを所蔵している図書館が少ないのでpdfを公開してもいいんじゃ、と個人的には思う)
→pdf化されたそうです。http://www.kyoto-bhutan.org/ja/Himalayan/
■文献検索
ネパール独自の検索サイトはないようなので、世界、日本で使われている検索サイトを書きます。これ以外にも文献を検索するデータベースはありますが、有料で大学に所属していないと使えないものが多いので、ここでは無料で誰でもどこでも使えるもののみを書きます。日本や英語圏の国で書かれ出版されたネパール関連の本や論文はもちろん検索できるが、ネパールで出版された本や論文は検索に引っかかることも引っかからないこともあるので、バックナンバーを一つ一つ探す必要がある場合も。また、アカデミックな内容の本は大学や研究機関の所蔵が多いですが、絵本、漫画、小説、料理の本などは大学の図書館よりも市立図書館などの公立の図書館の方が多いこともあるので、探すものによって使い分けたほうが良いと思います。
・google scholar
http://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja
世界中の文献を探す
・worldcat
http://www.worldcat.org/
世界中の文献を探す
・NACSIS Webcat
http://webcat.nii.ac.jp/
主に日本で出版されたり、日本の大学や研究機関にある文献を探す
Webcat is a system for searching the union catalog database of books and journals held by the Japanese libraries of universities and other institutions.
・cinii
http://ci.nii.ac.jp/
主に日本で書かれた本、論文、博士論文を探す。日本語が多いが一部英語のものも。
CiNii (Scholarly and Academic Information Navigator, pronounced like "sigh-knee") is a database service that enables searching of information on academic articles published in academic society journals or university research bulletins, or articles included in the National Diet Library's Japanese Periodicals Index Database.
・カーリル
https://calil.jp/
市立図書館、県立図書館の横断検察ができます。
・外務省外交史料館
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/
・アジア歴史資料センター
http://www.jacar.go.jp/
【イギリス】
・The British Library
http://www.bl.uk/
・The National Archives
http://www.nationalarchives.gov.uk/
・Copac National, Academic, and Specialist Library Catalogue
http://copac.ac.uk/
イギリスのwebcatのような。
【アメリカ】
・Library of Congress
http://www.loc.gov/index.html
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/nptoc.html
・The University of Chicago Library
http://www.lib.uchicago.edu/
・SARAI
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/southasia/cuvl/
・The U.S. National Archives and Records Administration
http://www.archives.gov/
■文献目録

発展途上地域日本語文献目録―アジア 中東 アフリカ ラテンアメリカ オセアニア (2002)
- 作者: アジア経済研究所図書館
- 出版社/メーカー: 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 発売日: 2005/04
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 日本ネパール協会
- 出版社/メーカー: 日外アソシエーツ
- 発売日: 1984/12
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 薬師義美
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 1994/11
- メディア: 大型本
- この商品を含むブログを見る
■その他
国立国会図書館 アジア諸国の情報をさがす
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/
アジア研究情報GATEWAY
http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/asj/index.html#redirected
日本ネパール協会
http://nichine.or.jp/
会員になると図書室が使える。